
金融犯罪コンプライアンスの真のコスト,2023 年アジア太平洋地域調査
アジア太平洋地域における金融犯罪コンプライアンスにかかるコストを調査
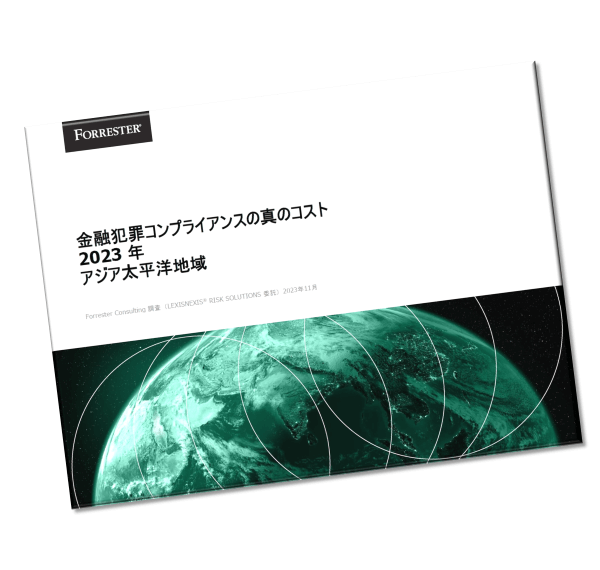
最新の「金融犯罪コンプライアンスの真のコスト調査、2023年アジア太平洋地域」では、オーストラリア、中国、インド、日本、シンガポールの5市場の回答者を対象に調査を実施しました。調査によると、金融犯罪コンプライアンスの総コストは2023年に450億ドルの大台に近づくと予測されます。
金融犯罪のコンプライアンス・コストが最も高いのは中国と日本で、それぞれ約204億ドルと178億ドルに達します。調査結果の深堀により、APAC地域では人件費(41%)とテクノロジー(32%)が大きな影響を及ぼしていることが明らかになりました。これらの要因の背景には、金融犯罪規制の強化、規制当局の要望、銀行・金融危機の余波、e-KYCを含むデジタル化などが挙げられます。
主なハイライト:
- コンプライアンス・コストの分解:中国が204億ドル、日本が178億ドルでAPAC地域内ではトップ。人件費(41%)とテクノロジー(32%)が極めて重要な影響を及ぼしており、これは規制の強化、金融危機、デジタル化などが背景にあります。
- 課題の把握:規制当局への報告、制裁対象者やPEPsの特定、口座開設のためのKYCなどが主な課題となっています。金融機関の課題を理解することにより、今後の戦略立案に不可欠な知見を得ることができます。
- ビジネス機会: 金融機関は、KYCプロセス、内製コンプライアンス・ソリューション、データクオリティの向上、取引モニタリング、AMLの強化を、今後数年間の間に計画しています。それにより、商品の合理化、効率性の向上、コラボレーションの改善などを目指しています。金融機関が計画する活動を把握することは、戦略立案に不可欠です。
- Forresterによる専門的分析: Forresterの有調査専門知識によって、より確実なAPACにおけるコンプライアンス・シナリオを理解することができます。
この調査が重要な理由
コンプライアンスが金融機関の業務にとって極めて重要な要素となっている現在、本調査は表面的な問題にとどまらず、金融機関がAPAC地域でコンプライアンス・プログラムを導入する際に直面する複雑な問題を解き明かしています。金融のプロフェッショナル、業界の専門家にとって、本調査はより深い理解をお手伝いいたします。
レクシスネクシス・リスク・ソリューションズが持つ豊富な知識を活用し、APACにおけるコンプライアンスの真のコストについて、より包括的な視点を提供しております。本調査は単なるレポートではなく、金融機関がコンプライアンスの課題を効果的に解決するための戦略的ツールです。
フォームに必要事項を入力し、資料をダウンロード
興味を持たれる可能性がある製品
-
Bridger Insight® XG
規制上のコンプライアンスの合理化、お客様のビジネスの保護と収益の向上を実現
詳細はこちら -
Firco™ Compliance Link
単一のソリューションで、口座、海外送金、貿易取引のスクリーニングを管理
詳細はこちら -
Firco™ Trade Compliance
貿易金融スクリーニングでスピードと精度を向上させます
詳細はこちら -
WorldCompliance™ Data
高リスクの個人と団体に関する堅牢なデータベース。
詳細はこちら -
WorldCompliance™ Online Search Tool
制裁、PEP、アドバースメディア (ネガティブ・ニュース)に対するワンストップソリューション
詳細はこちら
